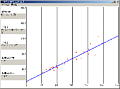



画像をクリックすると拡大表示されます。
拡大画像からはブラウザの「←戻る」ボタンで戻ってください。
これも以前に仕事で経験した木材の計測に関するネタです。
建築に使われる木材は含水率15%程度のものが望ましいです。
これ以上水分があると、後で狂いを生じ、これ以下に乾燥させると材が傷みます。
木材の含水率を計測するには全乾法が使用されます。
まず計測する木材の重量を計り、次に、この木材をオーブンで完全に乾燥させ、重量の変化より含水率を求めます。
ただし、完全に乾燥させるので破壊検査となってしまいます。
そこで、他の方法で計測した同一サンプルを全乾法にかけて関係を求めておきます。
多数のサンプルを用いて統計的に検量線を求め、この検量線から含水率を求めます。
我々が行ったのは木材を電極で挟んで静電容量を求め、この値から含水率を求める方法です。
この方法を用いた装置が製品化されている関係で、具体的な回路やソフトを紹介する事はできません。
ここでは、検量線作成ソフトにデータを入れ、全乾法と静電容量測定の関係をグラフ表示してみました。
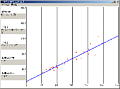 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
| 含水率と静電容量の関係 | データ入力ダイアログ | 検量線グラフの印字 | 入力データの印字 |
このソフトは測定データより検量線を求めるもので、ビジュアルC++6.0で作成しました。
エクセルを使うより簡単に検量線を求めることが出来、ファイルとして保存出来ます。
横軸は全乾法による含水率、縦軸は同一サンプルの静電容量を示します。
当然ながら先に静電容量を計測し、次に全乾法で含水率を計測します。
静電容量と含水率が比例関係にあるのがわかります。
この一次方程式を使えば静電容量から含水率を求める事が出来ます。
尚、メモにダミーデータとありますが実際に計測されたデータの一部を抽出したものです。
当時はグラフを手書きしてスケールで検量線を引いたり、エクセルを使用したりしていました。
その後、最小二乗法の勉強をした時に、このソフトを作ってみました。
データの入力や変更はテンキーを使って簡単に行えます。