

電池を電源とした機器を製作するときのデバッグ用電源として製作しました。
このとき、最初から電池を使って試験するのは危険です。
電池は内部抵抗が低いので、試作回路に誤りがあった場合、大電流が流れる可能性があります。
電流を制限出来る定電圧電源が必要になります。
出力電圧は1.5V〜9Vとしました。
出力電流は100mA、150mA、200mAの3段階に絞れるようにしました。
ただし、この電流値は部品のバラツキや周囲温度により、若干、変動します。
回路図をクリックすると拡大表示されます。
拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。
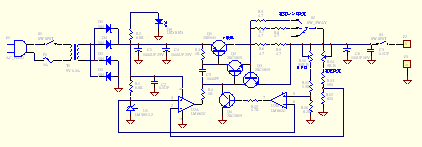
回路は簡単なシリーズレギュレータです。
OPアンプLMC662で基準電圧と出力電圧を分圧した値が等しくなるように制御します。
電流制御はトランジスタ1石の簡単なものですので、精度は良くありません。
OPアンプの半分が余ったので、過電圧保護(OVP)を付け加えました。
VRで簡単に電圧が変えられるので、うっかり高い電圧を出してしまわないように、半固定VRで最大電圧値を設定して
おきます。
こうしておけばメインVRを回し過ぎても出力電圧は制限されます。
今回、全て手持ちの部品を使いましたが、電源トランスに余裕がありません。
AC9V0.3Aのものですが、整流した直流電流は最大で、せいぜい0.2A程度です。
(損失を無視し、大雑把に言えば、電圧が√2倍に充電され、電流は1/√2となる)
このような小型のトランスを定格ギリギリで使った場合、電圧変動が大きくて大変です。
少しでも電圧降下を減らそうと、整流ダイオードはショットキを使用しています。
それでも、整流電圧は10.9V程度まで落ちるので、9Vに対して1.9Vの余裕しかありません。
本当は出力にダーリントンでないNPNトランジスタが欲しかったのですが、手持ちが無かった為、インバーテッドダーリントン
にしてベース電圧を畳み込みました。
OPアンプLMC662は出力電圧を電源電圧近くまで出せるので好都合です。
ただし、このOPアンプの入力同相電圧は電源電圧より低くなっているので注意が必要です。(出力のみレールtoレール)
今回の回路では、入力側は1.25Vですので問題ありません。
逆に無負荷状態ではトランスの電圧が上がり、今度はLMC662の電源電圧の最大値が問題になります。
今回、無負荷ではLMC662の電源電圧が14.85V程度になりました。
LMC662の電源電圧の最大値は16Vですので、電圧の高いトランスを使用した場合、電源ピンの保護が必要になって
きます。
電流制限用の抵抗の値に対し、制限された電流値が少し大きいような気がしますが、これはOPアンプが出来るだけ出力を維持
しようとしてQ3に電流を供給してしまうからだと考えられます。
インバーテッドダーリントンになってしまった為、本来の出力電圧制御の電流が小さくて済み、OPアンプの出力に余裕が出来て
しまった為だと思われます。
Q1の損失は最大で2W程度になりますので、軽く放熱が必要です。
回路上の問題を色々書きましたが、使用上は全く問題は無く、電池の代わりとして十分に使えます。
 |
 |
|---|---|
| 製作した電源 | 電源内部 |