



画像をクリックすると拡大表示されます。
拡大画像からはブラウザの「←戻る」ボタンで戻ってください。
余っていた大きな大きなプラスチックケースを再利用しようとした所から話がスタートしました。
以前、このケースには「ラジオ少年」で販売していた4球電池管スーパーが入っていました。
何年か前、真空管ラジオに興味を持ったとき手始めに「ラジオ少年」から4球電池管スーパーのキットを2台購入しました。
1台は真空管用のIFTを使用したもの、もう1台はトランジスタラジオ用のIFTを使用したものでした。
それぞれケース(実際はプラスチックのパーツボックス)が付属していましたが真空管IFTを使用した方は寸法が大きく
付属のケースに収まりませんでした。
そこでホームセンターに少し大きなケース探しに行ったのですが手頃なサイズが無く、かなり大きなケースを購入することに
なりました。
このケースにラジオとAC電源を組み込みました。
2台のラジオを比較してみると何とトランジスタラジオ用のIFTを使用した方が感度が良く、音量も大きかったのです。
結局、真空管ラジオ用IFTを使用した方はケースから取り外されケースだけが残りました。
ここにFMラジオを組み込んだ訳です。
現状、実用的に聴くことが出来るのは93.9MHzと88.8MHzの2局のみです。
根本的な問題もあり、このまま打ち切りになる可能性もあるのですが、ここまでの経緯を記録しておきます。
回路図をクリックすると拡大表示されます。
拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。
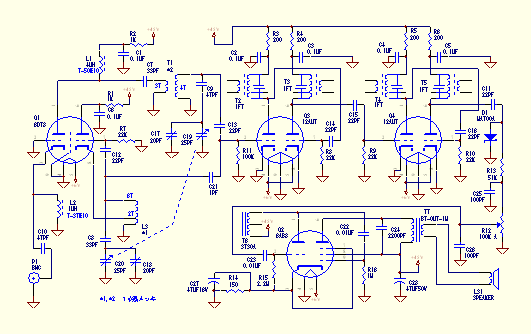
前回、5極管8球を使用したFMスーパーを製作し、まずまずの結果が出たのですが今回はケースの形状から8球は無理ですので
複合管4球で回路を書きました。
B電圧は45Vに設定しました。
50V耐圧のコンデンサーを使いたいのが主な理由ですが。
トランジスタラジオ用のIFTを使うので高い電圧を掛けたくないということもあります。
感電したくないということもあります。
最初、6DT8を3本と低周波に6AB8を1本を使ったのですが感度不足で失敗でした。
回路図は何度も書き直し現在の回路で、やっと2局が聴けるところまできましたがこれ以上は難しいと思います。
一つは使用した球の問題、もう一つは構造的な問題でコイルとバリコン、外付けトリマの配線が綺麗に出来なかった点です。
前回は高周波、中間周波部分に5極管の6AJ5や6AK5を使ったのですが、これらの球は低いB電圧でもプレート電流が
流れやすかったという点があります。
特にトランジスタ用のIFTはインピーダンスが低く2mA〜3mA程度流さないとゲインが出ません。
ところが手持ちの6DT8や12AT7では1mA程度しか流れません。
手持ちの真空管は種類が少ないのですが12AU7が2mA近く流れる事が判ったので中間周波増幅を12AU7に
代えました。
3極管はグリッド電流が多く流れるようです。
それでグリッドリークバイアスが深く掛かりプレート電流が流れにくくなっています。
グリッド抵抗を22KΩと低くし、現状では2.5mA程度のプレート電流が流れています。
実験では電流の流れにくい6DT8でもグリッドとカソードを両方接地すればプレートに2.6mA流れました。
回路図で入力のバッファは直流的には、この状態ですので実際に2.6mA流れています。
グリッドに正バイアスを掛ける方法も試してみました。
確かにプレート電流が増えますが、経験が浅く、この方法を使って良いのかどうか判断出来ません。
6BC8という球を試してみようとしたのですが入手出来ませんでした。
兎に角、中間周波増幅でゲインを稼げるかどうかに掛かっています。
入力バッファは非同調のグリッド接地アンプです。
私はゲインを測定する機器を持っていませんがシグナルジェネレーターとオシロでの波形確認では、そこそこの
ゲインがあるようです。
局発はコルピッツ発振が確実ですが部品点数の少ないカソードタップ式にしました。
前回はトロイダルコアと6AK5で問題なく発振したのですが今回は発振が弱く、周波数を測ろうとすると発振が止まって
しまいます。
コイルをQの高い空芯コイルに変更しました。
こうすればディップメーターも使えます。
ただ空芯コイルは取り付けに制約があり、バリコンとの配線が面倒になったりして、なかなか上手くいきませんでした。
コイルを造りかえたり取り付け場所を変えたり試行錯誤を繰り返しました。
今回のラジオはウオームアップに時間が掛かり状況を複雑にしました。
電源を頻繁に入り切りした場合、動作不良と勘違いして調整点を動かしてしまうので調整が上手くゆきません。
電源を入れて30秒程度で音が出始めるのですが音量が小さく、音量が定常になるまでには5分程度は掛かります。
低電圧で無理矢理電流を流している為かもしれません。
現在、低い周波数で受信できていないのは局発が、まだ完全でない可能性があります。
検波は相変わらずスロープ検波です。
これでもAMのスーパー程度の音は出ますので面倒な他の検波方式を試そうと思ったことはありません。
通常はAGCを掛けるのですが今回はゲインに余裕が無く12AU7のグリッド抵抗が小さいこともあり
AGCを省いています。
音声出力は6AB8を使用しました。
B電圧45Vでは大きな音は出ませんが室内で聴くには十分です。
B電圧45Vでは熱暴走の心配が無く、負荷が3極部、5極部ともトランスですのでカソードを直接接地しても良いと
思います。

もう少し詳しい記録が別のページ
電子回路とソフトウエア > 電源関係 > DC6V定電圧電源
にアップされていますのでここでは写真と回路図のみアップします。
6.3V 2A のヒータートランスからDC6Vを発生する定電圧電源です。
入出力電圧差が1V以下になるので多少、面倒です。
DC6V出力では多少リップルが出るので現在、出力を5.8Vに設定しています。
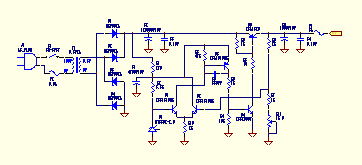

もう少し詳しい記録が別のページ
電子回路とソフトウエア > 電源関係 > 6V−45V30mAコンバータ
にアップされていますのでここでは写真と回路図のみアップします。
DC6VからB電圧(DC45V30mA)を発生するDC/DCコンバータです。
効率73.3%、無負荷電圧48.4V、出力短絡電流44mAで連続短絡に耐えます。
銅テープでシールドした箱に収納します。
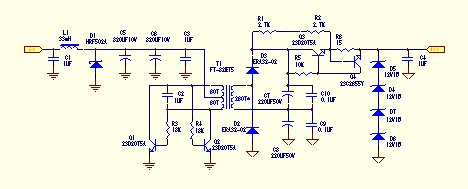
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
| ラジオ正面 | 下から見た内部 | 上から見た内部 | バリコン周辺 |
古いラジオから流用した大きすぎるケースですが余裕を持った配置が可能で製作、調整には助かりました。
真空管は省電力の球ですが大きい内容積は発熱対策にも有効です。
スピーカーとバーニアダイアルは動かさないという事で配置を決めました。
結果、真空管の取り付けが逆さになりました。
動作上は問題無いのですが見た目が少し悪いです。
最初に書いたように現在、93.9MHzと88.8MHzの2局しか実用的に聴けません。
93,9Mzは電波の状態が良く受信出来て当然という感じですが88.8MHzは電波の状態が地形の関係で
それ程良くなく、これが実用的に聞こえるということは、可能性は感じます。
一旦、作業は打ち切りますが6BC8等、別の球が入手出来たら再度挑戦するつもりです。
トラッキング調整も、もう少し正確に行う必要があります。
今回は回路の手直しやコイルの作り直しに時間をとられすぎました。
下の写真は作り直したコイル(失敗作)と試したIFTです。

FMスーパーで感度を上げるには中間周波増幅でゲインを稼ぐことが重要になります。
ところが低いB電圧とトランジスタラジオ用のIFTでは厳しいものがあります。
IFTを分解してコンデンサーの容量を測ったところ50pF程度でした。
10.7MHzに共振するインダクタンスは4.4uH程度になります。
かなりインピーダンスが低く、多少、電流を流さないとゲインが得られないようです。
最初、6DT8を使用しましたがプレート電流は1mA程度でした。
低い電圧で電流が流れやすい12AU7に換えたところ電流が2mA近く流れ、高い周波数の一部の局が聞こえるように
なりました。
12AU7は手持ちがが少なく他の用途に回したので再度6DT8に戻しました。
プレート電流を増やす為にグリッドに+2.5Vのバイアス電圧を加算しました。
実際のグリッド電圧はグリッドリーク電流で下がり、約−0.1V程度でした。
これでプレート電流は2mA強となりました。(最初の3組のIFT)
最後の1個のIFTには、さらにAGC電圧を加算しているので2mA以下です。
回路図をクリックすると拡大表示されます。
拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。
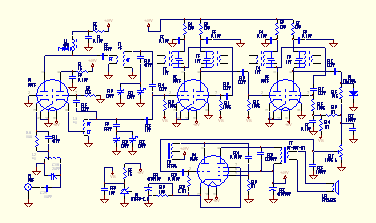
ローカル局は全て受信出来るようになりましたがコミュニティー局は聴けません。
ロッドアンテナは正確に方向を合わせる必要があります。
全体的に音が小さく、まだまだ改良の余地があります。
その後の実験で感度が低いのは中間周波増幅でゲインが稼げない為だと判りました。
原因は双3極管を使った事にあります。
3極管と5極管ではゲインが大きく違いました。
今回のタイトル「4球FMスーパー」では改良の余地が無いのでここで打ち切ります。
実験結果は別のページ「電池管FMラジオの実験」にアップする予定です。
このページは電池管でFMラジオを作る為の予備実験の記録を残す場所としてスタートしました。
電池管FMスーパーは1機種を製作し記事としてアップする事が出来ました。
ただし電池管は性能が低く発展性が無いので途中から傍熱管を使ったFMラジオの為の実験に内容が変わっています。