



画像をクリックすると拡大表示されます。
拡大画像からはブラウザの「←戻る」ボタンで戻ってください。
最近、DSPラジオチップが各種、出回っているようです。
今回、Si4825−A10というチップを入手したので早速ラジオを作ってみました。
最初にデータシートとアプリケーションノートを入手します。
チップ名を入力して検索すればメーカーサイトに到達するので
* データシート Si4825-A10Rev0_1.pdf (2023年4月現在)
* アプリケーションノート AN738.pdf
をダウンロードします。
参考回路を見ると同調回路が無いのに気付きます。
バリコンや同調コイルがありません。
特にFMラジオではバリコンやコイル回りの配線に悩まされますが、その心配は不用です。
面倒なトラッキング調整も必要ありません。
実際、配線終了後、何の調整も無く放送を聴くことが出来ました。
試作と言えども常に実際に使用することを考慮して製作します。
まず収納するケースを決めます。
タカチのSW−125Sという比較的小型なプラスチックケースを使うことにしました。
周波数帯はFM専用に割り切りました。
回路図をクリックすると拡大表示されます。
拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。

チップは41点の周波数帯域を選択出来ます。
選択にセレクタを使わず1CHのA/D変換入力で済ませています。
従ってピン数が少なくて済む代わりに高精度の分圧抵抗を必要とします。
今回はFM1バンドだけですので分圧抵抗はR8、R9の2個だけです。
R8は270K1%と30K1%の金属皮膜抵抗を選別し直列抵抗として−0.5%以内に収めています。
R9は180K1%と18K1%の金属被膜抵抗を選別し直列抵抗として−0.5%以内に収めています。
ただし今回購入したSi4825−A10というチップは76MHz〜95MHzという選択肢がありません。
ワイドFMを聴く為には76MHz〜108MHzというバンドを選択するしかありません。
76MHz〜90MHz、87MHz〜108MHzの2バンドにする方法もありますが分圧抵抗を増やしスイッチで切り替える
必要があります。
選局は基準電圧を100KΩのボリュームで分圧した電圧をA/D変換しています。
76MHz〜108MHzとした場合、95MHz〜108MHzは不用となるのでボリュームの回転角の1/3以上が
遊んでしまいます。
そこでボリュームと並列、直列に抵抗を入れています。
これはFMの1バンドのみであるため出来ることで複数のバンドを使っている場合は他のバンドに影響を与えてしまいます。
尚、Si4825−A20というチップが入手出来れば76MHz〜95MHzの選択肢があります。
当地はKMIXとNHKFMとSBS補完局が聞こえます。
SBS補間局は電波が強く受信は楽ですがKMIXとNHKFMは送信所の谷間にあり2個所づつ聞こえますが電波が弱く
選局がクリチカルでした。
そこでプリアンプを付けてみました。
効果はあるようで選局が楽になりました。
ただ、同調周波数が固定の為Qを高く取ると同調点より離れた周波数で逆効果になります。
チップには電子ボリュームが内蔵されているのですが、これを使わず外付けのボリュームで音量を調整します。
ステップアップ端子とステップ端子の極性で出力レベルは4段に固定されます。
この接続では出力は最大に固定されています。
低周波アンプはMC34119を使いました。
ゲインを設定出来、発振しにくいので使い易いアンプです。
ただし、BTL出力となりスピーカーのマイナス端子がGNDから浮くので支障のある場合があります。
今回、DSPチップの出力を最大に固定している為アンプのゲインをもう少し低くした方が良かったと思います。
音量には余裕があるのでボリュームを少し絞っています。
反転入力端子に信号を入力している例が多いのですが非反転端子に入力すれば入力インピーダンスを高く出来ます。
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
| 基板部品面 | 基板半田面 | ラジオ外観 | ラジオ内部 |
チップは秋月電子で購入した変換基板に実装してユニバーサル基板に取り付けています。
変換基板は片面ですので裏側に銅箔を貼ってGNDに接続しています。
ケースは樹脂ですが内面に基板と同寸法のアルミ板を貼り付けています。
アンテナ基板間は1.5D2Vを半田付けしていますが他は全てコネクタ接続ですのでメンテナンスは容易です。
ケースは扱いやすい寸法だと思います。
感度はアンテナの長さの影響を受け、伸長時55cmのロッドアンテナを装着すれば市販のポケットラジオより若干良いように
感じます
プリアンプの感度は大したことはなく、全範囲に効くわけではないのですが同調点を適当な周波数に固定すれば
効果はあります。
プリアンプ無しでも受信出来たのですがアンテナの向きによっては受信をミスする事がありました。
現在、受信出来る局はNHKFMが2個所、KMIXが2個所、SBSの補完局が1個所です。
音量は十分実用的で音質も良いのですがスピーカーがミニサイズですので限界はあります。
室内の特定の場所で出力20W、距離が15Km程度のコミュニティー局が実用的に聞こえます。
ちょっと離れた場所では全く聞こえません。
市販のラジオでも同じ傾向があります。
消費電流は音量によって大きく変わります。
普通に効けば100mA以下ですので単3電池2本で連続24時間位は動作すると思います。
上記のポケットラジオでコミュニティー局(FM島田)を室内で安定的に聴くには大変です。
当地はFM島田のカバー範囲外です。
静岡方面のコミュニティー局は地形の関係で出力的に希望がありません。
そこでFM島田を実用的に聴けるラジオを作ってみました。
寸法が大きくなってポータブルと言ってもポケットには入りません。
まず、FMを88MHz〜108MHzと76MHz〜90MHzの2バンドに分けました。
スパンを狭くして選局を少しでも楽にします。
ついでにAMバンドも追加し3バンドになっています。
それからFMプリアンプを改良してみました。
回路図をクリックすると拡大表示されます。
拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。
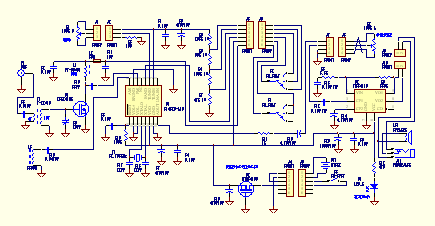
3バンドになったのでバンド切り替えスイッチを追加しました。
プリアンプは2SK241Yから2SK241GRに変更しソース抵抗も省いたので7.5mA程度流れています。
AMの時はプリアンプの電源を切ります。
AM用バーアンテナが必要になります。
10φ×70mmのフェライトバーに0.07mm×7芯のリッツ線を巻きました。
450uH以下の適当な値で良いので気楽に巻けます。
実測値で365uHでした。
選局は普通の270度回転のものを使いました。
ただし頻繁に使う物ですので国産24φのBカーブを使いました。
350円から400円程度です。
選局が結構クリチカルなので最初、ポテンショメーターを使う予定で購入しました。

ポテンショメーターが1800円、専用バーニアダイアルが1000円しました。
ところが14回転もしなければならずダイアルも見にくく操作性が悪く止めました。
取り付けも面倒です。
音量ボリュームは外国製16φのAカーブで100円以下です。
スイッチ付きで無ければ動かすことは殆どありません。
 |
 |
 |
|---|---|---|
| ラジオ外観 | ラジオ内部 | 基板部品面 | >
ケースは手持ちの小型パーツボックスです。
透明ですので電源表示灯は基板に付いています。
ロッドアンテナは伸長38cmの小型のものですがBNCコネクタで交換出来ます。
ポータブルDSPラジオ2号機で試聴エリア外のコミュニティー局が実用的に聴けるようになりましので1号機でも
安定に聴けるように作り直しました。
基板は作り直しましたがボディーは流用しました。
1号機では76MHz〜108MHzを1バンドで選局していたこともあり非常に選局がクリチカルでしたので
2号機のように76MHz〜90MHz、88MHz〜108MHzの2バンドに分けました。
あとはプリアンプの出来具合です。
DSPチップは非常に感度が良くローカル局を聴くだけならプリアンプがあっても無くても変わりません。
しかしコミュニティー局を聴くには効果があります。
回路図をクリックすると拡大表示されます。
拡大図から本文に戻るにはブラウザの←戻る釦を使用してください。
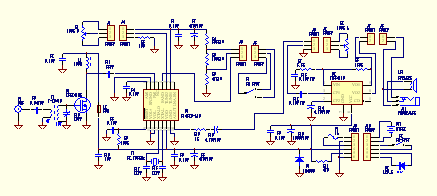
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
| 基板部品面 | 基板半田面 | ラジオ外観 | ラジオ内部 |
コミュニティー局が室内で実用的に聴けるようになりました。
ただ筐体が小さい為か若干、周辺ノイズを受けやすいような気がします。
その後スピーカー自体に問題があることが判明しました。
また、スピーカーが小さい為か音が少し硬いような気がします。
スピーカーを交換しスッキリした音になりました。
音量は十分余裕があります。
感度は非常に良いです。
以前ホームセンターで1300円で購入したポケットラジオと比較してみました。
ポケットラジオは屋外ではコミュニティー局を聴くことが出来ますが私の仕事部屋では全く聞こえません。
製作したDSPラジオはプリアンプ無しで仕事部屋で聴く事が出来ますがノイズ気味となります。
プリアンプを接続すると(回路図通り)他のローカル局同様にクリアーな音質で聴く事ができます。